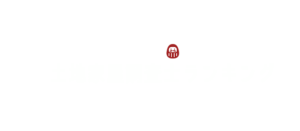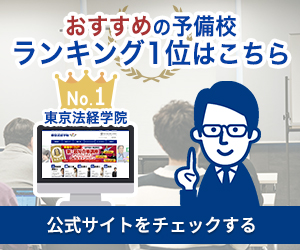今回は、土地家屋調査士が独占業務をもっているメリットについてご紹介していきます。
土地家屋調査士の受験を考えている方の中には、土地家屋調査士がもっている独占業務に、具体的にどんなメリットがあるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、土地家屋調査士の独占業務にどんなメリットがあるのかについてまとめました。土地家屋調査士を目指そうと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
土地家屋調査士とは?
土地家屋調査士とは、土地や建物などの不動産を調査・測量し、所有者を確認したうえで不動産の登記手続きを行う職業のことです。
不動産の登記にはさまざまな種類がありますが、土地家屋調査士が対応するものは土地の建物の広さや形といった物理的なものがメインです。
土地家屋調査士の業務と聞くと「作業服を着て、現場に行って測量をする」といった現場仕事のイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際は登記手続きや製図の作成、計算作業といったデスクワークも対応業務に含まれるため屋外・屋内の両方で業務を行います。
また、個人が所有している土地の範囲のことを「筆界」といいますが、この筆界を測量・調査する「筆界特定の手続」も土地家屋調査士の業務です。
隣接する土地があると、土地の所有者同士が土地の所有権を巡ってトラブルになることが多々あり、ときには裁判に発展することがあります。
このような個人間の土地のトラブルを解決するためには筆界を明確にする必要があり、筆界調査委員といわれる専門家も含めて測量・調査を行います。
土地家屋調査士は、正確な測量・調査を行う現場仕事や、集中力が求められるデスクワークなどが主業務となるため、計画的に活動することが求められる職業だといえるでしょう。
土地家屋調査士の独占業務
特定の資格を保有している者しか対応することが認められていない、専門性が高い業務のことを「独占業務」といいます。
以下で紹介するものは土地家屋調査士の独占業務となっているのでチェックしてみてください。
独占業務①土地や建物の測量・調査
土地や建物の不動産を測量・調査する業務は、土地家屋調査士の独占業務です。
測量を行う際は、指定の土地や建物の状態を確認するだけではなく、建物の所有者を含めた立会人の意見などを参考にしながら慎重に進める必要があります。
独占業務②不動産の表示に関する登記の申請手続の代行
測量・調査の結果を踏まえ、建物の表示や土地の分筆などを登記する一連の作業のことを、「不動産の表示に関する登記の申請手続」といいます。
不動産の表示に関する登記の申請手続の代行ができるのは、土地家屋調査士だけです。
本来この手続きは不動産の所有者が行わなければならないのですが、手続きが煩雑で難しいことから、土地家屋調査士が申請手続きを代行できるようになっています。
独占業務③筆界の調査・特定
土地が登記された際に、土地の範囲を区画するために定めた境界線のことを「筆界」といいます。
自分の土地の筆界がわからないという所有者は多く、住宅を建てられずに頭を悩ませていることや、土地を巡って隣人とトラブルになることも少なくありません。
このようなトラブルを解決するために、筆界を調査・特定する業務も土地家屋調査士の独占業務です。
土地家屋調査士が独占業務をもっているメリット
土地家屋調査士は、不動産の「表記に関する登記」の申請を独占業務としている国家資格です。それでは、土地家屋調査士の独占業務にどんなメリット3つを見ていきましょう。
独立開業がしやすい
1つ目のメリットは、独立開業がしやすいということです。不動産の所有者が登記を行う際には、必ず「表記に関する登記」をすることが義務付けられています。そのため、土地家屋調査士は、建物を建てたりその用途を変更したりした場合に発生する業務を独占的に担うことになるので、独立開業がしやすいというメリットがあります。
就職や転職に役立つ
2つ目のメリットは、就職や転職に役立つということです。土地家屋調査士は不動産登記に関わる独占業務をもっているため、不動産関係の会社や土地家屋調査士事務所など、必ず土地家屋調査士を置いておかないといけない会社が数多くあります。そのため、採用条件に資格必須と記載されている場合も多く、就職や転職に有利になるのもメリットです。
需要が安定している
3つ目のメリットは、需要が常に安定しているということです。土地家屋調査士の独占業務は、建物の新築・増築・用途や構造の変更・取り壊しなど、不動産全般にかかわる業務内容のため、需要が安定してあるのもメリットです。その一方、資格試験の受験者数は年々減少しているため、狙い目の資格とも言えます。
土地家屋調査士の独占業務のメリットは、非常に大きい
いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、土地家屋調査士が独占業務をもっているメリットについてご理解いただけたと思います。
土地家屋調査士の独占業務は、需要が安定している不動産登記にかかわる部分なので、非常にメリットの大きい資格です。土地家屋調査士を目指そうと考えていた方は、ぜひ参考にしてみてください。
当サイトでは土地調査士の資格取取得をお考えの方のために、おすすめの土地調査士の予備校をランキング形式で紹介しています!良かったらチェックしてみてください。