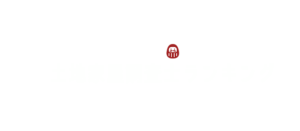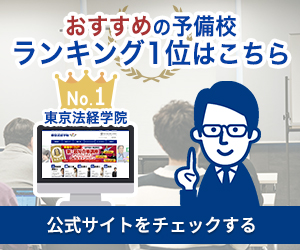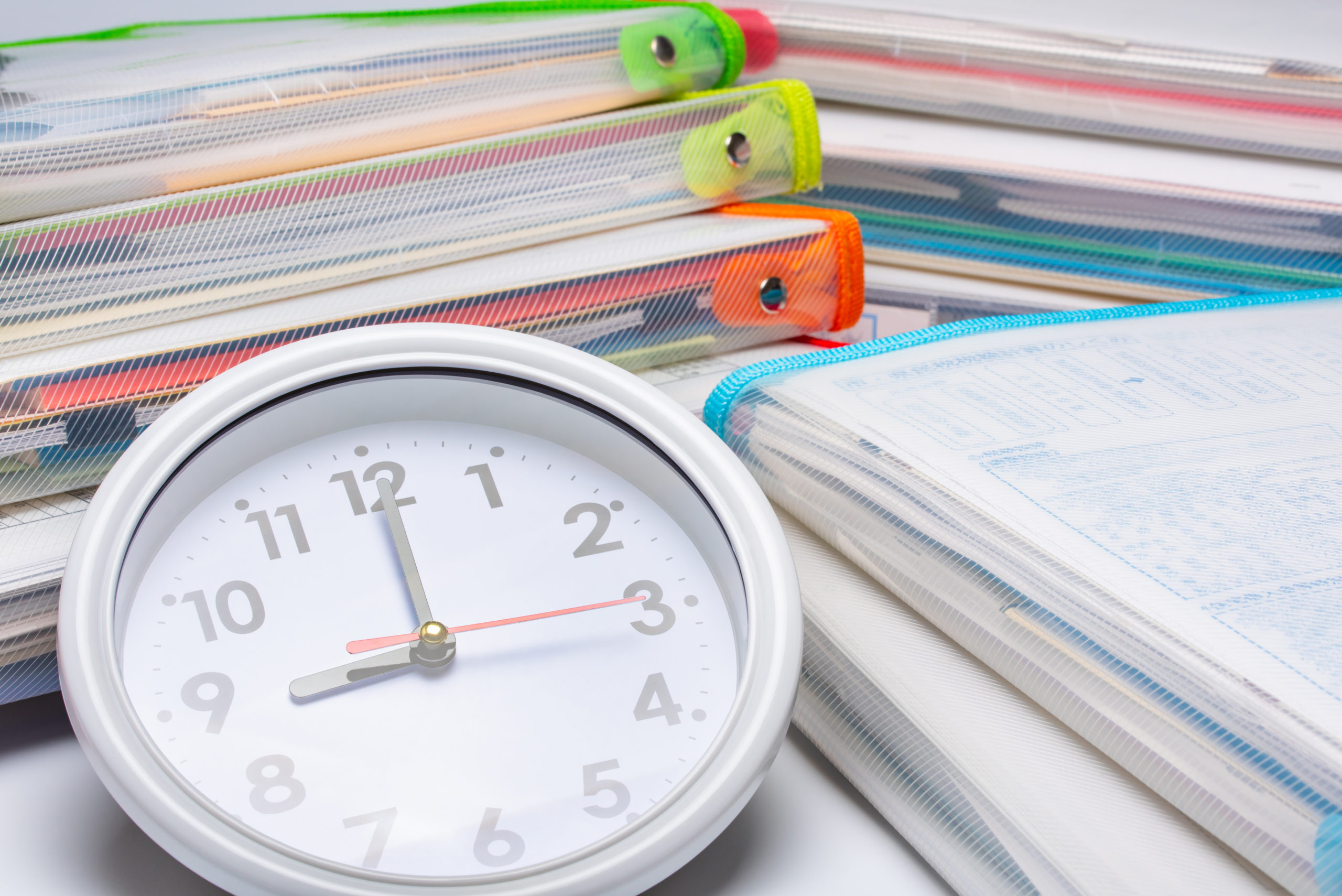
この記事では、土地家屋調査士の資格取得を目指す方のために、必要な勉強時間と勉強法のコツについて紹介します。
勉強時間を把握しておくことで、逆算した勉強時間の確保やスケジュール調整がしやすくなるでしょう。
また、勉強時間から算出し、自身の苦手科目に重点を置いたり、独学ではなくスクールに通ったり、学び方を考えることができます。
最短で合格を目指すならいきなり勉強を開始するのではなく、まずはこの記事を読んで必要な勉強時間を把握し、適切な方法で勉強をしましょう。
Contents
土地家屋調査士合格に必要な勉強時間は約1,000時間~
土地家屋調査士試験に合格するためには、一般的に独学で勉強した場合約1,000時間以上の勉強が必要だといわれています。
社会人の場合は、仕事をしながら勉強することも多いため、なかなか時間の確保が難しいでしょう。
平日に2時間、休日3時間勉強すると仮定しても、約1年半の道のりです。
また、1,000時間程度を確保したからといって、必ず合格できるわけではありません。
建築や不動産、法律などの予備知識が一切ない方が受験を試みる場合は、1,500時間程度みておくと安心です。
忙しい方は合格に向けて勉強時間の配分を調整
土地家屋調査士資格の合格基準は、基準点のクリアと相対評価の両方を満たす必要があるため、より多くの加点が必須になるでしょう。
そのためには、自分の得手不得手に分けて勉強時間の配分をすると効率よく学ぶことができます。
「択一問題」
民法や不動産登記法などから20問、択一式で出題されます。
暗記問題がメインのため、反復で覚える必要がありますが、暗記であれば移動時間などの隙間時間を勉強に充てることも可能でしょう。
択一問題は1問2.5点とみられており、加点比重が大きいため確実に加点できるように勉強時間の確保が必要です。
「書式問題」
書式で出題される問題は、土地と建物から各1問です。
公表はされていませんが、書式は1問0.5点から1点の配点予想がされており、択一より加点割合が小さいのが特徴です。
計算や作図など手間がかかる書式で加点を狙うより、加点比重の大きい択一に勉強時間を割く受験者が多いでしょう。
勉強時間の配分は1年~2、3年ベースで調整
土地家屋調査士は難関国家資格であり、令和2年度の合格率は10.36% でした(小数点第二位以下四捨五入)。
また、合格までの平均受験回数は5回以上が最も多いというデータもあります。
そのため、2~3年かかることを見据えた勉強時間の調整をしておく必要があるでしょう。
土地家屋調査士合格のための勉強時間の目安1日どのくらい?
土地家屋調査士の勉強時間は、1日あたり2~3時間が目安です。
資格取得のために必要な勉強時間は、トータルで1,000~1,500時間とされています。
そのため、1日あたり2~3時間という目安は、1年半に渡り資格のための勉強を行う場合の時間です。
1年半ほどの学習期間を設けることが一般的ではありますが、より短期間で土地家屋調査士合格を目指したいという場合は、1日あたりさらに多くの勉強をしなければなりません。
土地家屋調査士試験の勉強方法にはどのようなコツがいる?
ここからは、土地家屋調査士試験を受験する方へ向けて、効果的な勉強方法について解説します。
土地家屋調査士試験は、択一と書式という2種類の試験科目の勉強が重要であるといわれています。
択一は法律関係の択一問題で、書式は土地と建物に関する記述の問題です。
土地家屋調査士試験をパスするために、どのような勉強方法を行えばよいのでしょうか。
択一問題である民法の勉強から着手しよう
土地家屋調査士試験の勉強では、まず民法の概念について、しっかりと理解することが大切です。
不動産にまつわる登記や調査において、民法は避けて通れない重要な要素です。
土地家屋調査士試験で出題される問題は、民法に関する知識がベースとなります。
そのため、択一試験に出題される民法の勉強から着手することで、以後の学習が非常にスムーズに進む可能性が高いでしょう。
民法は意外と勉強量が多いため、ほかの分野の勉強時間に支障が出ないように、時間をかけすぎないことがポイントです。
ひと通り内容を理解したら、択一問題のメインとなる不動産登記法の勉強に取りかかるようにするとよいでしょう。
書式問題は、電卓・定規の扱いに慣れておく
書式問題では、本格的に過去問に触れる前に、電卓と定規の扱いに慣れておくとよいでしょう。
書式問題は非常に難易度が高く、電卓や定規を使い慣れていないと更に時間がかかってしまう可能性があります。
電卓を使った放射計算や定規を使った作図、申請書を写す作業などを繰り返し練習して、基本的な動作を滞りなく行えるようにしましょう。
基本となる書式のやり方をマスターして過去問に挑戦してくださいね。
過去問を繰り返し解く
土地家屋調査士試験の勉強では、過去問を有効的に活用しましょう。
まだ勉強を始めたばかりという段階でも、択一問題の過去問を積極的に解くことで、出題される問題の傾向を掴みやすくなるからです。
択一問題の過去問を解くときには、間違った問題や理解できなかった問題をそのまま放置せず、テキストを読み返してしっかりと復習することが肝心です。
択一問題の過去問を解いて正答率が上がったと感じたら、書式問題の過去問に取り組むことをおすすめします。
書式問題の過去問を解く場合、最初は時間に制限をつけずに、じっくり向き合うとよいでしょう。
わからない部分や間違えた箇所は、解説を読み込み、わかるまで繰り返し解きなおすことがポイントです。
土地家屋調査士合格のためには勉強時間を効率よく使おう
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、土地家屋調査士資格に合格するために必要な勉強時間や勉強方法がご理解いただけたと思います。
土地家屋調査士は難関国家資格であるため、合格するためにはしっかり勉強時間を確保しましょう。
また、土地家屋調査士試験は専門的で特殊な知識が必要となるため、基本となる民法の知識を頭に入れるところから始めて、徐々に書式の問題に慣れることが大切です。
過去問を繰り返し解いて、効率的に勉強を進めてくださいね。
当サイトでは土地調査士の資格取取得をお考えの方のために、おすすめの土地調査士の予備校をランキング形式で紹介しています!良かったらチェックしてみてください。