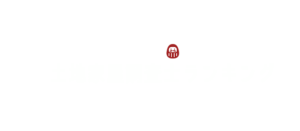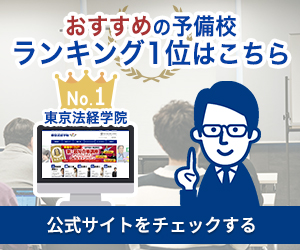「土地家屋調査士で独立開業するには、どのくらい期間が必要?」
「土地家屋調査士で開業しても、あまり稼げない?」
土地家屋調査士は、独立開業が可能な国家資格の士業です。
土地や家屋(建物)について調査し、所有者が誰なのか、登記(権利関係を公示する手続き)をおこないます。
土地家屋調査士の業務について「日本土地家屋調査士会連合会」は以下のように定義しています。
- 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
- 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
- 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
- 筆界特定の手続について代理すること。
- 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。土地家屋調査士を目指す人は、将来的に独立開業も考えている方も多いと思います。今回の記事では、土地家屋調査士が独立開業するメリット・デメリットと、成功するポイントについて解説します。
Contents
土地家屋調査士が独立開業するメリット
土地家屋調査士は、独立を前提とした資格職といわれています。
開業には実務経験年数の条件はなく、資格を取得すれば独立が可能です。
企業などの組織に属さず、独立開業する3つのメリットを紹介します。
独立開業する3つのメリット
- そもそも独立開業しやすい
- トライアンドエラーを実行しやすい
- 高年収を目指しやすい
そもそも独立開業しやすい
土地家屋調査士は、資格を取得すれば、実務経験年数に関係なく独立開業できるのがメリットの1つです。
個人事務所の開業や、他の土地家屋調査士と共同で会社を設立するなど、多くの土地家屋調査士が自営で活動しています。
法律上は、資格取得後すぐに開業が可能ですが、数年以上の実務経験を積んでから開業する場合が多いです。
なぜなら、経験を積みながら業務内容を覚え、開業資金を調達し、人脈づくりができるためです。
独立しやすいからこそ、しっかりと準備して、失敗なく開業できると安心ですね。
トライアンドエラーを実行しやすい
「もし独立開業に失敗したら、土地家屋調査士の仕事ができなくなる?」と心配ではありませんか?
結論から述べると、独立開業に失敗しても、再就職や転職は可能です。
たとえば、開業に失敗した後、どこかの企業で再就職したとします。
再就職先で改めて経験を積み、人脈を広げ、資金をつくれます。
強く望めば、失敗を活かして学び、再び独立開業を目指せるでしょう。
高年収を目指しやすい
独立開業した場合、自分のさじ加減で受注を調整できるため、高収入が目指しやすいです。
土地家屋調査士の平均年収は約600万円とされており、一般的なサラリーマンよりも高収入の傾向があります。
独立する場合、個人事務所を開業するのか、会社を設立するのかによって、年収は異なるでしょう。
独立した場合としない場合
独立していない場合、平均年収は500〜600万円といわれており、全体平均と大きな差はありません。
一方、独立開業して事業が軌道に乗っていれば、年収1,000万円以上になる可能性もあります。
自営であるからこそ、頑張るほど高収入を目指しやすいです。
しかし、独立開業しても、技術や経営知識が十分でないなどのケースにおいて、年収600万円以下になる人もいます。
独立して高収入を目指したいなら、実務経験を積み、経営知識をつけるのが大切です。
個人事務所で成功した例
成功されている方の例として、年間で3,000万円、最大で4,500万円の売上があったケースがあります。
経営者以外にも職員がいる個人事務所なので、売り上げから人件費と経費を引く必要がありますが、年収1000万円以上の高収入の実例です。
実際に成功している人がいると、独立開業の魅力を感じますね。
土地調査家屋士が独立開業するデメリット
土地家屋調査士の独立開業は、3つのメリットがある一方で、デメリットもあります。
開業を検討するならば、メリットだけでなく、デメリットも考慮しましょう。
独立開業する2つのデメリット
- 自分の案件受注力が問われる
- 景気に左右されやすく収入が不安定に
自分の案件受注力が問われる
独立開業する十分な技術があっても、開業しただけでは顧客は集まりません。
案件を受注するためには、さまざまな営業活動が大切であり、大変な努力が必要です。
たとえば、表示登記の無料相談会をおこなうのも、営業活動の1つです。
独立開業に成功した方は、WEBやSNSを活用したマーケティングを実施しているケースも少なくありません。
土地家屋調査士としての自分を、知ってもらう機会を多くつくりましょう。
また、自分を売るための独自性を模索したり、業務のクオリティを高める努力も大切です。
技術がともなっていなければ、受注に至らない場合も考えられます。
自分の案件受注力を高める努力は、継続的におこなうのが望ましいでしょう。
景気に左右されやすく収入が不安定に
土地家屋調査士の仕事は、住宅の建築・増築や、公共工事の増加にともなう、測量や表示登記の案件受注が大半です。
好景気のときは活発な不動産取引も、不景気では停滞するため、景気に左右されやすい仕事なのはデメリットになります。
独立開業するときは、景気の動向や需要をみるための知識も必要です。
独立開業後に成功するポイント
土地家屋調査士が、独立開業に成功するには、5つのポイントがあります。
独立開業後の失敗を避けるためにも、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
成功する5つのポイント
- まず就職して実務経験を積む
- 相談できる先輩や同期合格者との繋がりを持つ
- 独立前に人脈を広げておく
- 開業までにかかる費用と開業後のコスト
- ダブルライセンスは開業の際に有利
まず就職して実務経験を積む
資格を取得すれば、独立開業ができる土地家屋調査士ですが、まずは就職して実務経験を積むのがおすすめです。
その大きな理由は、実務を経験して覚える必要があるためです。
覚える業務とは、実際の調査方法や、業務上必要なコミュニケーションの取り方などが挙げられます。
そのほか、測量※やCAD(Computer Aided Design)※など、みて覚えておくべき項目もあります。
※測量:物の高さ・深さ・長さ・広さ・距離を測る作業)
※CAD:パソコンを使った図面の作成・設計
就職して仕事に就いても、先輩などのサポートなしで全ての実務をおこなえるには、少なくとも2〜3年は要すでしょう。
土地家屋調査士が扱う不動産は、大きな資産であり、業務上での失敗がないよう努めなければなりません。
相談できる先輩や同期合格者との繋がりを持つ
独立前に就職していれば、先輩や同期との縁があり、独立後も繋がりを持つのが可能です。
独立開業後は、トラブルなど、過去に経験しなかった業務も発生する場合があります。
困ったときに相談できる先輩がいたら、対処法を教えてもらえて心強いですよね。
また、同じタイミングで独立する同期がいれば、情報交換もしやすいでしょう。
独立前に人脈を広げておく
独立に向けて、人脈を広げておくのもポイントの1つです。
人脈を広げるには、相手との信頼を構築するのがとても大切になります。
業務上の失敗をしないだけでなく、円滑でていねいなコミュニケーションが必要です。
土地家屋調査士が繋がりたい人脈は、売買中心の不動産屋、ハウスメーカーなどが挙げられます。
信頼関係が構築できれば、定期的な案件の受注がしやすいでしょう。
開業までにかかる費用と開業後のコスト
土地家屋調査士の開業資金の目安は、300〜400万円とされています。
どのような形で開業するか、どこで開業するかによって、必要な費用は変わります。
当面の運転資金や生活費の見積もり
独立開業しても、すぐに案件を受注できるとは限りません。
軌道に乗るまでは、ある程度の運転資金が必要になります。
運転資金の金額は、人によって異なります。
たとえば、生活費を準備するなら、家族構成・家族の収入状況によって、必要な金額が変わります。
もし、事業資金の融資や、機材購入時にローンを組んでいたら、毎月の返済が必要になります。
生活費や返済費用を見積もって、必要な金額の準備をしましょう。
測量に関する初期費用も多めに
土地家屋調査士の業務には、以下のような道具が必要です。
業務に必要な主な測定機材
- トータルステーション
- GPS
- 三脚
- ミラー
- CADソフト
- パソコン
- プリンタ
上記の機材で約250〜280万円、全てしっかりしたものを揃えようと思うと、1,000万円近くになる場合もあるようです。
費用をかけるべき機材を厳選し、中古も賢く利用すれば、費用の節約になります。
オフィスの家賃も必要
開業する際、事務所を構える場合は、家賃や光熱費などの固定費がかかります。
事務所をどこに構えるかによって、家賃相場は異なります。
もし、自宅で仕事をするならば、家賃が必要ない分の開業費用を軽減できるでしょう。
ただし、測定機材一式の保管場所は必要になるため、倉庫や物置の準備を検討しましょう。
土地家屋調査士の独立の初期費用
独立開業において、必要な初期費用・コストの目安は以下のとおりです。
| 自分ひとりで仕事をしていく(事務所を構えない)場合 | ||
| 土地家屋調査士連合会 | 登録手数料 | 25,000円 |
| 入会金 | 5万円 | |
| 毎月の会費 | 約1万円 | |
| パソコン・プリンタ・実務ソフトなど | 約250~280万円 | |
| 測定器具(一式) | 約20~30万円 | |
| そのほか 文具や名刺など | 約5万円 | |
| 合計 約285~325万円 | ||
上記以外に、必要に応じてかかる費用
- 事務所を構える場合の賃貸料と光熱費など
- 移動手段につかう自動車などの購入費と維持費
- スタッフを雇う場合の人件費
- 当面の運転資金や生活費
ダブルライセンスは開業の際に有利
ダブルライセンスとは、複数の資格を持つことです。
土地家屋調査士のほかに、別のスキルがあると、付加価値がついてアピールできます。
特に、土地家屋調査の業務に関わる資格であれば、あなた一人で完結するサービスの幅が広がるため、顧客からも喜ばれるでしょう。
ダブルライセンスにおすすめの資格は、司法書士や行政書士です。
司法書士
司法書士とは、不動産ならびに会社の登記を中心に、法律事務をおこなう国家資格です。
土地家屋調査士との共通点は、不動産登記を仕事とする点ですが、取り扱う内容は異なります。
| 司法書士 | 土地家屋調査士 |
| 権利の登記をおこなう | 表示の登記をおこなう |
| 不動産の権利を持つのは誰で、どんな内容の権利化を示す | 不動産の面積・建物の種類など、物理的な状況を調査・測量して示す |
土地家屋調査士と司法書士のダブルライセンスは、一連の登記を1人で請け負えるため、収益が上がります。
顧客にとっても、一度に依頼ができるため利便性が良く、同業者との差別化が図れるでしょう。
行政書士
行政書士は、店舗の開業・会社の設立などに必要な公的書類や、遺言書などの権利義務に関わる民事書類の作成をおこなう職業です。
土地家屋調査士との共通点は、顧客の依頼に基づいた手続きや作業を代行する点ですが、請け負う内容は異なります。
| 行政書士 | 土地家屋調査士 |
| 公務員として携わる | 法務省職員として携わる |
| 役所に申請する登記書類の作成代行 | 法務局に申請する登記書類の作成代行 |
たとえば、農地転用申請や開発許可申請は、法務省と役所の両方で手続きが必要ですが、一連の手続きを1人で請け負えるメリットがあります。
土地家屋調査士として独立開業するまでの流れ
土地家屋調査士が独立開業するときの手順は、以下のとおりです。
独立開業するまでの流れ
- 土地家屋調査士試験を受けて合格する
- 実務経験を積む
- 土地家屋調査士連合会に登録する
- 測定機材や事務用品・名刺などの手配をはじめる
- 税務署に個人事業主開業届を出す
- 事業スタート
資格を取るだけでなく、「2.実務経験を積む」が開業後に成功するポイントです。
また、土地家屋調査士として活動するためには「3.土地家屋調査士連合会に登録する」は必須項目です。
そして、独立開業には「5.税務署に個人事業主開業届を出す」も忘れてはいけません。
独立時の注意点
独立開業するにあたって、失敗を避けるために、以下の注意点を確認しましょう。
独立時の注意点
- 受注のめどをチェック
- 人材確保と仕事のお願い先はあるか
受注のめどをチェック
開業で失敗する原因は、「案件がない」「思うように案件受注ができない」などの、受注のめどが立たなくなったケースが多いです。
失敗を避けるためには、独立する前に、受注のめどがどの程度つくか、人脈から案件受注の当てがあるか、しっかり確認しましょう。
ここで、独立前の勤務で広げた人脈が活かされます。
人材確保と仕事のお願い先はあるか
土地家屋調査士の業務は、1人では難しい作業もあり、特に測量に関しては、人材の確保が望まれます。
加えて、困ったときの相談先があるのか、業務を手伝ってもらえる繋がりがあるかなど、ここでも人脈が大切となります。
まとめ
土地家屋調査士は、専門知識が必要な国家資格であり、独立開業しやすい職業です。
案件受注力を高める努力次第で、高収入も目指せます。
成功するためには、実務経験を積みながら資金を貯めて、相談できる横のつながりや、クライアントなどの人脈を広げるのがポイントです。
また、ダブルライセンスは開業に有利なため、相性の良い資格の取得も目指してみましょう。
当サイトでは土地調査士の資格取得を考えている方のために、おすすめの土地調査士の予備校をランキング形式で紹介しています。
ぜひチェックしてみてください。