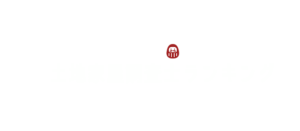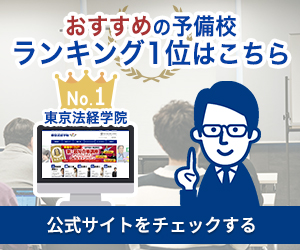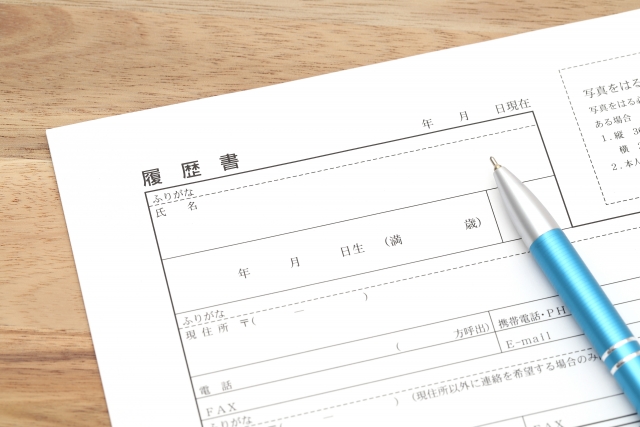
土地家屋調査士として働くには登録が必要!申請方法や登録費用
土地家屋調査士になるには、難関である土地家屋調査士試験に合格しなければなりません。
しかし、試験に合格しただけでは、調査士として就業できないことをご存じでしょうか?
調査士として働くためには、登録手続きが必要であり、これを忘れてしまうと、せっかく取得した資格も活かせません。
そこで本記事は、土地家屋調査士の登録申請の方法を紹介します。
試験合格後の流れまで把握しておきたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
土地家屋調査士として働くには登録が必要
土地家屋調査士として就業するためには、試験合格後に「日本土地家屋調査士会連合会」の土地家屋調査士名簿に登録されなければなりません。
登録に関しては、『土地家屋調査士法』第3章第8条および第9条において、以下のとおりに定められています。
第三章 登録
(土地家屋調査士名簿の登録)
第八条 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士会連合会(以下「調査士会連合会」という。)に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。
(登録の申請)
第九条 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
つまり、ご自身の事務所を置く地域を管轄する法務局の管轄区域にある調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出し、受理されると正式に調査士になれるのです。
調査士会連合会の登録とあわせて、この土地家屋調査士会への入会も必要になります。
次項からは、これらの手続きの具体的な申請方法を、順を追って解説します。
引用元:「土地家屋調査士法」第3章第8条,第9条
土地家屋調査士会の登録や入会の方法
ここからは、日本土地家屋調査士会連合会の登録および、土地家屋調査士会への入会の方法を手順ごとに分けて説明しますので、参考にしてみてください。
手順①登録時の必要書類を準備する
土地家屋調査士会連合会の登録には、複数の書類を提出する必要があります。
登録申請を行う際は、まず以下の書類をそろえましょう。
【土地家屋調査士会連合会の登録時の必要書類】
- 土地家屋調査士試験合格証
- 土地家屋調査士登録申請書
- 登録申請書の写し
- 履歴書
- 身分証明書
- 登記されていない証明
- 写真(4枚)
- 誓約書登録免許税の金額に相当する収入印紙または登録免許税を納付した旨の領収証登録
- 本籍記載の住民票の写しまたは戸籍抄本もしくは戸籍記載事項証明書および本籍記載なしの住民票の写し
なお、最後の「本籍記載の住民票の写しまたは戸籍抄本もしくは戸籍記載事項証明書および本籍記載なしの住民票の写し」は、所属する調査士会ごとに提出するものが異なります。
上記の書類にくわえて、調査士会連合会から別途指定された書類がある場合は、その書類も添付してください。
手順②入会時の必要書類を準備する
土地家屋調査士会への入会手続きにも、用意すべき書類があります。
提出する書類は、入会する調査士会によって異なるため、就業する地域の調査士会の公式ホームページ、または電話での問い合わせで確認しましょう。
ただし、入会届や印鑑届はほとんどの場合で必要です。
入会届は多くの場合、各調査士会のホームページから書式をダウンロードできるので、比較的簡単に入手できます。
手順③土地家屋調査士会に連絡する
必要書類の用意が完了したら、就業する地域の土地家屋調査士会に連絡し、登録申請書類の提出日を伝えましょう。
事前に連絡することで、調査士会に都合のよい日程を調整できるほか、書類に不備がないかどうかも確認できます。
「時間をかけて提出に行ったのに、二度手間になってしまった……」という事態にならないためにも、大切な手順の1つです。
手順④土地家屋調査士会に書類提出と諸経費の支払いを行う
予定した日に土地家屋調査士会に出向いて必要書類を提出し、登録や入会にかかる諸経費を支払ったら、手続きは完了です。
登録が完了するまでには、1~2週間ほどかかります。
完了の知らせがあるまでは、調査士として就業できないので、しばし連絡を待ちましょう。
土地家屋調査士会の登録・入会費用
前述したように、土地家屋調査士になるための登録や入会には、手数料をはじめとした諸経費がかかります。
金額は入会する調査士会によって大きく変わりますが、18万~24万円が相場です。
まとまったお金を用意しなければならないので、直前になって工面できないといったことがないようにしましょう。
登録や入会の費用の内訳の例は、下記のとおりです。
【調査士になるための諸経費の内訳の例】
- 登録手数料:2万5千円
- 登録免許税:3万円
- 会館建設負担金:5万~10万円
- 表札札:8千~1万6千円
- 入会金:5万円
- 月々の会費:1万2千~1万6千円
登録手数料の金額は、土地家屋調査士法で一律に定められているものの、そのほかの費用は調査士会ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
また月々の会費も、調査士会によって、毎月徴収したり、前期後期に分けて年に2回徴収したりするなどルールが異なります。
土地家屋調査士会にすぐに登録しないとどうなる?
土地家屋調査士の登録には、多くの書類や高額な費用が必要なため、「合格してもすぐには登録できない」という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、登録申請を先送りすると、何か不都合が生じるのではないかと不安になってしまいますよね。
結論から言うと、登録が遅れることによって、調査士の資格が失効することはないため、合格後すぐに登録を行わなくても、何ら問題はありません。
安心して、ご自身の最適なタイミングで登録申請を行ってください。
ただし、登録を先延ばしにすることで、同時期に資格を取得し、すぐに登録を終えて仕事を始めた人とキャリアに差がついてしまいます。
ですから、資格取得後はできるだけ速やかに実務を始め、調査士としての経験を積むことをおすすめします。
土地家屋調査士の登録申請には書類と諸経費の確認が大切
いかがでしたでしょうか。
土地家屋調査士の試験に合格しても、土地家屋調査士会を通して、日本土地家屋調査士会連合会への登録を済まさないと、正式に就業することはできません。
これには、調査士会連合会の登録とあわせて、調査士会への入会手続きが必要になります。
調査士の登録を行う際や、調査士会に入会する際には、登録申請書や履歴書、そして入会届などの書類を用意します。
必要書類がそろい次第、調査士会に提出日を連絡することを忘れないようにしましょう。
当サイトでは土地調査士の資格取取得をお考えの方のために、おすすめの土地調査士の予備校をランキング形式で紹介しています!良かったらチェックしてみてください。