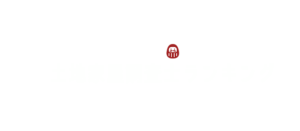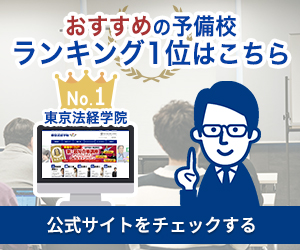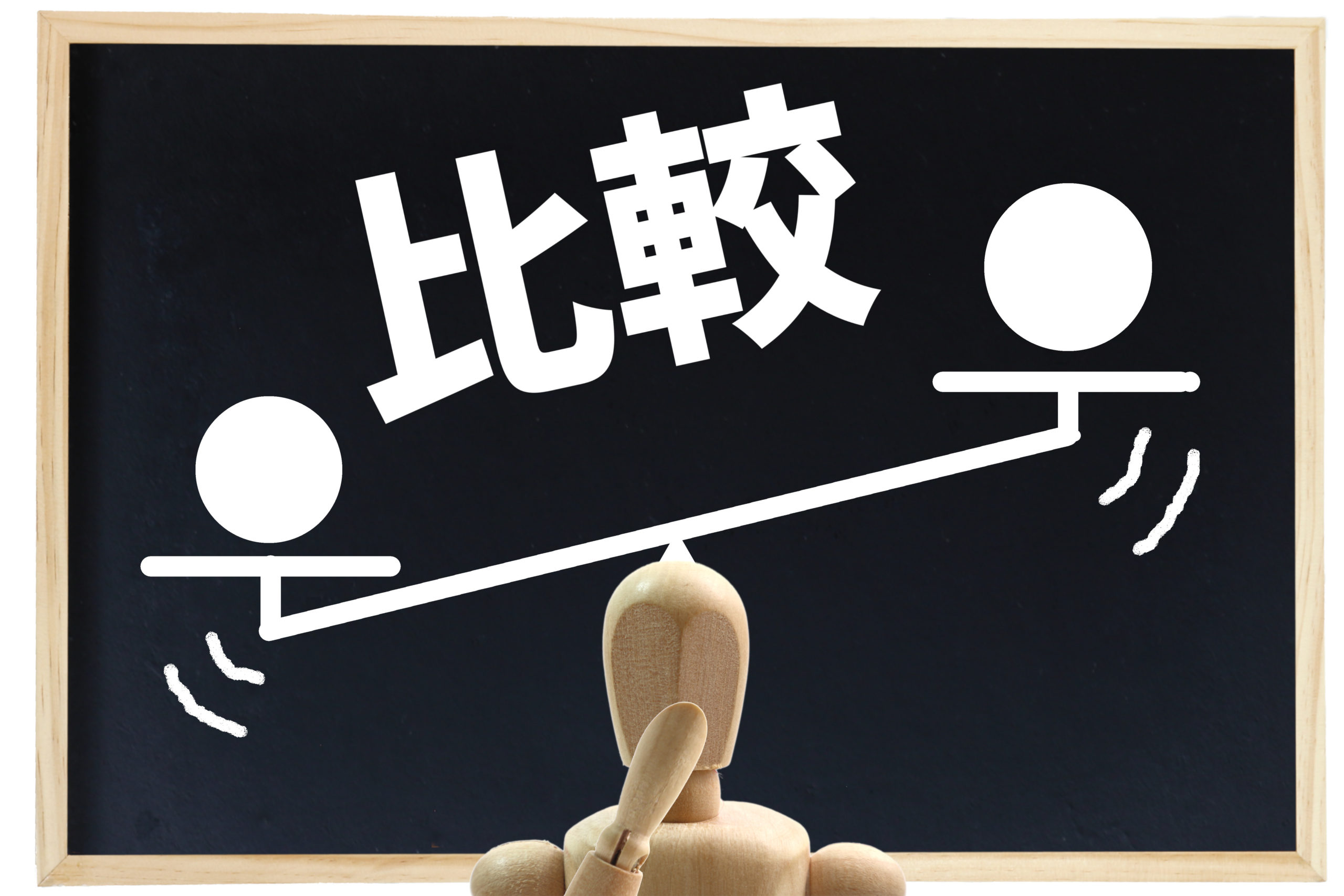
土地家屋調査士と不動産鑑定士は、どちらも不動産業界には欠かせない国家資格です。
資格の名称は似ていますが、仕事の内容には大きな違いがあることを知っていますか?
そこで今回は、土地家屋調査士と不動産鑑定士が、それぞれどのような資格でどのような業務を行っているのかを、わかりやすくご紹介します。
土地家屋調査士と不動産鑑定士の違いがわからない、それぞれの業務内容が知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。
土地家屋調査士の主な業務内容
土地家屋調査士は、土地や家屋の現況を明らかにし、登記を目的とする測量や調査、申請の手続きを代理することなどを主な業務としています。
土地家屋調査士の主な業務
・登記目的で土地または家屋に関する調査や測量をすること
・登記の申請手続きを代理すること
・土地の境界を決定するための手続きを代理すること
・登記に関する審査請求の手続きを代理すること など
不動産鑑定士の主な業務内容
一方で不動産鑑定士は、地理的状況や市場経済などのさまざまな要因を踏まえ、不動産の経済価値を鑑定・評価します。
不動産鑑定士の主な業務
・土地や建物などの不動産の経済価値を鑑定すること
・「不動産鑑定評価書」を作成すること
・不動産の調査、分析、コンサルティング業務 など
土地家屋調査士と不動産鑑定士の違い
土地家屋調査士は、土地や建物の測量および登記に関するプロフェッショナルです。
誰もが安心して不動産取引が行えるよう、不動産の現況を明確に登記記録に反映する役目を担っています。
ただし、不動産の価値について調査することはありません。
対して、不動産鑑定士は不動産の経済価値を決定する専門家です。
鑑定評価は不動産鑑定士のみが行える業務であり、高度な専門知識を必要とします。
なお、不動産を鑑定する際に、土地家屋調査士が作成した資料や登記事項を基に評価を行う場合もあります。
これが、土地家屋調査士と不動産鑑定士の業務上の接点ともいえるでしょう。
両者とも不動産業界で仕事をする資格であり、接点がない訳ではありませんが、その業務内容は大きく異なるようです。
資格の名称は似ているが、業務内容は全く違う
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、土地家屋調査士と不動産鑑定士の違いがご理解いただけたと思います。
登記を行うのが土地家屋調査士、不動産価値を鑑定するのが不動産鑑定士であり、業務内容は大きく違います。
どちらの仕事が自分に合っているかを見極め、資格取得を目指してみてください。
当サイトでは土地調査士の資格取取得をお考えの方のために、おすすめの土地調査士の予備校をランキング形式で紹介しています!良かったらチェックしてみてください。